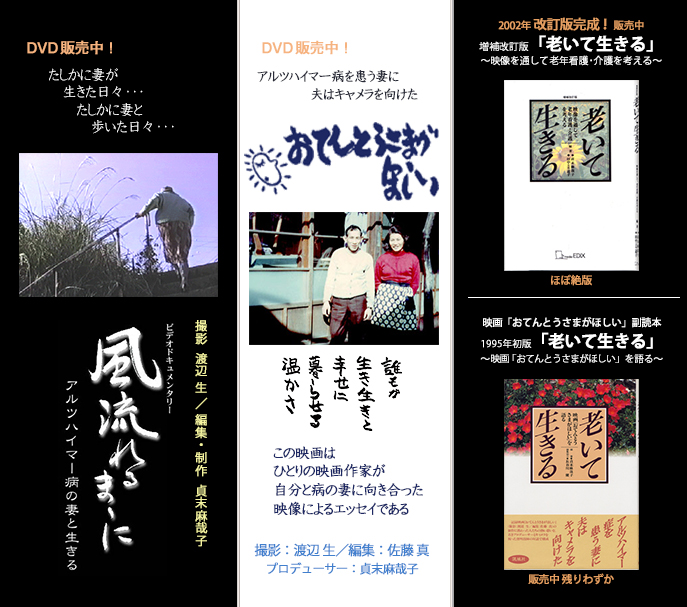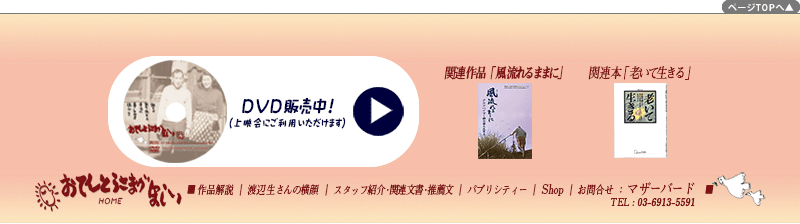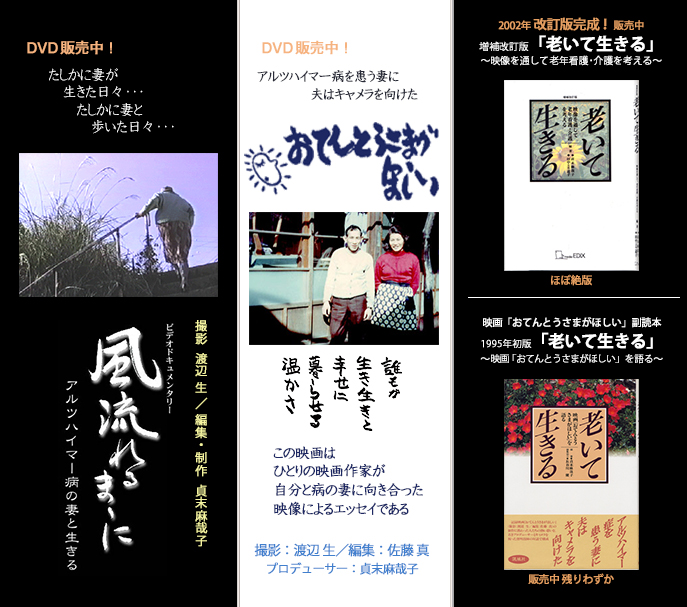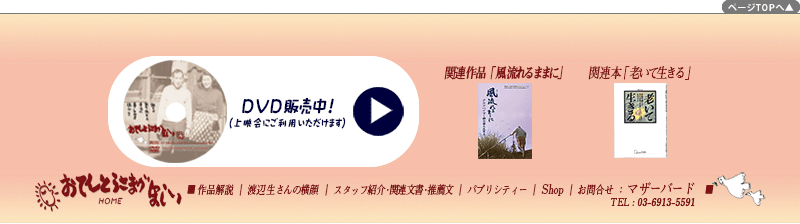1988年頃、トミ子さんに軽い痴呆の病状が現れ始め、1990年2月、トミ子さんの骨折による入院をきっかけに、いよいよ渡辺さんは東京の仕事場を引き払い、生活の基盤を日立に移した。
そして、1991年8月、トミ子さんはアルツハイマー病と診断される。
1992年12月に入院を余儀なくされるまで、この自宅での介護生活の様子・トミ子さんの病状変化などを、渡辺さんはプライベートビデオで克明に撮影していた。医師に、より詳しく正確に症状を伝えることが目的だった。
トミ子さんが入院して10日後、あまりにかわり果てたトミ子さんの姿に愕然とした渡辺さんは、ショックのあまりビデオカメラをトミ子さんに向けることができなくなってしまうが、仕事のない日は必ず病院にトミ子さんを見舞う生活が半年も経つと、渡辺さんの関心と視点は、老人医療・看護の現場が抱える問題や患者を支える家族の問題、地域の福祉に関する問題などに広がっていった。
そして、1993年7月、病院関係者・患者の家族にも正式に撮影許可を得て、中古キャメラを購入すると、渡辺さんは慣れない16ミリのムービーキャメラによるたったひとりで撮影を開始。一般公開することを目的に本格的に映画制作に取り組み始めた。
100フィート(約3分弱)の撮影済みフィルムが60本を越えた頃、介護に疲れた身体にムチ打って夜毎自宅でコツコツとフィルムの編集を重ねてきた渡辺さんから、仕上げのお手伝いを引き受けた制作委員会の手に、約60分に編集されたフィルムが委ねられた。
1994年に始まった仕上げ作業は、「阿賀に生きる」の監督・佐藤真氏によって、再構成・再編集され、最終的に作品は、渡辺さん夫妻の物語を軸に進行することになった。
ナレーションも渡辺さん自身に語ってもらい、1994年9月、撮影開始より2年を経て映画「おてんとうさまがほしい」は完成した。
| <追記>
1991年12月、アルツハイマー病と診断された私の妻・トミ子の入院生活が始まりました。茨城県日立梅ケ丘病院・老人性痴呆疾患センター。看病に通う毎日、治療・看護に携わる病院職員の方々がまごころをこめて患者さんたちをお世話する姿に触れることは、私にとって何にもかえがたい感動の連続でした。
そうした皆さんのお姿と、患者さんを支えるご家族のお姿をフィルムに記録したいと、1992年7月、私は16mmフィルムで撮影を始めました。
病気になった自分の妻を写すのは苦しいことではありますが、こうした太陽の温かさにもまさる施設がもっとできること願い、そして、老いというものと、共に生きることの問題を、何とかもっと多くの方々に考えて頂ければと願っております。
|
上記枠内の文章は、渡辺さんが完成後に当初の制作意図に記した追記である。
あきらかであることは、渡辺さんが記録しようとしたものは、医療・介護の現場で患者さんを支える周囲の人々の懸命な姿だった、ということだ。しかも、映画人として、常に裏方で現場を支えてきた渡辺さんにとって、自分自身が作品の前面にでる構成など、はなから念頭になかった ことは言うまでもない。
しかし、我々は、渡辺さんとトミ子さんが築き上げてきた人間関係の深さに心打たれ、フィルムに刻まれた渡辺さんの“思い”の力に、強烈に惹かれた。そして、渡辺さん自身で語られる“生”へのメッセージを伝えたいと思った。
このように、敢えて一部、渡辺さんの思いを犠牲にすることまでお許しいただいたこの映画は、ルーティンに捕らわれない渡辺さんの懐の広さに許されてはじめて可能になった仕事であることを明記しておきたい。
老いることと病むことと、人と人が関わり合って生きることの問題は、もはや渡辺さんから見れば孫同然の世代である我々にとっても、遠く先の問題ではない。この作品の上映活動によって、世代を越えた関係が全国各地でつくられることで広がることを願ってやまない。